波ばかりその冷たさに触れているやがては春になるだろう海
波打ち際を歩いている
まだ素足にはなれない
蹲って指先で触れる海
あれは十九の時だったか
波を怖れることもせず
胸まで浸かったことがある
青春は春なのに違いない
遠い日の記憶が蘇る
あれからどれほど生きてきたことだろう
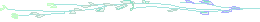
若い頃、「死」は夢のようなことであった。
死んだらすべてが終わるなどと考えたこともなかったのだ。
むしろ救われると思っていたのだろう。
悲しみも辛さもない。そこにあるのは「幸せ」なのだと信じていた。
あの日、父に結婚を猛反対されて泣きながら家を飛び出した。
家のすぐ裏には太平洋の大海原。打ち寄せる波の音が聴こえる。
私は裸足になり駆け出して行く。そうして波に揉まれて行く。
少しも怖いとは思わなかった。冷たいとも感じなかった。
ただ海の藻屑として消えようと決心していたのだと思う。
彼の声が聴こえた。私はやっと独りではないことに気づく。
海の中で抱きしめられた時、全身の力が抜けていくのを感じた。
生きてさえいれば幸せになれる。それはきっと永遠に違いない。
19歳の春私達は結婚した。その後の運命の波など知りもせずに。
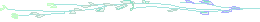
ここ数日、昔のことをよく思い出す。
「過去」と云ってしまえばなんだか「汚点」にさえ思える。
壊れてしまった玩具のようにもう修復が効かない。
どれほど生きて来たかよりもどれほど傷つけたかだろう。
私はもう取り返しのつかないことをこの世に残してきたのだった。
今は生きたくてたまらないけれど赦してもらえるだろうか。
将来を未来だと信じても良いのだろうか。
「墓場まで持って行く」とよく云うけれど
私には持ちきれないほどの罪が沢山あるのだと思う。
何一つ償いは出来ていない。ただ今ある命を全うするだけだ。
|