DiaryINDEX|past|will
| 2012年01月10日(火) | 北村透谷著「内部生命論」を読む |

1月の正津ゼミの課題テキストは北村透谷の著名な論文「人生に相るとは何の謂ぞ」と「内部生命論」になっている。前者の方は読んでも良く分からない。しかし、「内部生命論」はとても良く分かる。共感を覚える。それこそ、透谷の内部生命がこちらの内部生命を照らし、その熱さが移ってくるような「動き」さえ感じる。100年前以上も前に25歳の若さで自死した、その若者の言葉と語り口調に惹かれるものがあった。
だが、透谷が熱弁を奮って語っていることは、わたしとしてはすでに理解していることで、目新しいことでも何でもないという感覚も一方にある。
ということは、透谷が必死で伝えようとしたことが、その後100年ほどの年月を経て、わたしのような詩人でも哲学者でもない者さえ、それを自分の生き方や考え方の核にするほど、この日本の地にも行き渡ったということではないだろうか。
透谷の言う、被造物としての人間、被造物が創造者の声を聞くインスピレーションの存在、人間を人間たらしめるものが、その人間の固有の魂、つまりは内部生命であるといった思想を、今を生きるわたしたちは、自覚しないまでも、自分のものとしているのではないだろうかと、そんな気がしてくる。
透谷が主張することを、わたしたちは古今東西の文学者や哲学者、宗教家を通して知らされてきた、その思想を背後に持つすぐれた芸術作品に出合ってきた。そうした外からの影響や知識が自らの経験とひとつになり、透谷の言う「内部生命」が自分を自分たらしめていることを認識している人達はけっして少なくないのではないかと思うのだが・・・。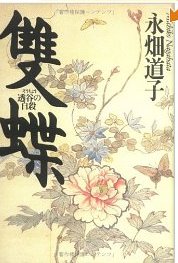
それにしても、このように「内部生命」について熱く語り、世の中に対して戦いを挑むというような強いエネルギーの持ち主が、この文章を書いた翌年に自死したのだろうか。
彼の死の理由を知りたくて、永畑道子著の「そう蝶ー透谷の自殺」を読んだ。
結婚生活への失望、恋心を抱いていた教え子の死、生活苦、本人の実力が評価されないことへの消沈、キリスト教会との確執、脳病に侵されつつあることへの不安と、ありとあらゆるストレスを抱えていたことを知る。
わたしは透谷の死の直接の原因は、そういったストレスから来る鬱病であったのだろうと思う。鬱病は自らの死を自分で止めることはできない病。
彼が自分の生き方や信仰に絶望し、それを捨てたというのでなく、彼自身の内部生命を精一杯傾けて、彼にしかできない仕事をやり通した、その結果としての死だったのだと思う。
この世での務めを終え、この世の向こう側にある世界へひょいと飛び立った。
短い一生だったが、彼の言葉はこうして今も生きている。彼の内部生命とこうして交流ができるということ自体が、彼が信ずる「霊魂不朽」ということを証明しているように思う。
以下は、自分の読解のためのノート
『人間は到底枯燥したるものにあらず。宇宙は到底無味の者にあらず。一輪の花詳(つまびらか)に之を察すれば、万古の思あるべし。造化は常久不変なれども、之に対する人間の心は千々に異なるなり。』
この論文はこんな文章で始まる。ここで使われている造化(ぞうか)という言葉に、後の文脈の中ではネイチャーとルビが振ってある。いきなり、宇宙である。自然である。そして彼は被造物である人間をネイチャーと並べて、その価値を解くのである。この自然賛歌、人間賛歌は、キリスト教の思想の故だと、また彼は断言する。
『吾人は人間に生命ある事を信ずる者なり。今日の思想界は仏教思想と耶教思想との間に於ける競争なりと云ふより、寧ろ生命思想と不生命思想との戦争なりと云ふを可とすー中略ー生命と不生命、之れ即ち東西思想の大衝突なり。』
と、生命を教えるキリスト教と生命を教えない仏教を対比し、彼がこれから説こうとすることがキリスト教の思想を背景に持つことをここで明らかにしている。
そして自分の使命は、キリスト教で言うところの生命の木なるものを人間の心の中に植え付けることだと宣言する。さらには生命を説かずに宗教は語れず、哲学も、信仰も、道徳も、政治的自由も、すべて生命を教えるものでなくてはその意味をなさないと言う。
そうした前起きをしたうえで、文芸上の生命の動機について語るのである。
美しくはあってもそこに思想のない文芸を否定し、思想はあっても芸術性のない文芸を否定し、勧善懲悪のピューリタニズムを否定する。透谷はキリスト教の信仰は持ち、伝道などのキリスト者としての役目を果たしつつも教会を批判している。教会の中にある、表面的なピューリタニズムが透谷の生き方とは合わないものだったからなのだろう。
『文芸は思想と美術とを抱合したる者にして、思想ありとも美術なくんば既に文芸にあらず、美術ありとも思想なくんば既に文芸にあらず、華文妙辞のみにては文芸の上乗に達し難く、左(さ)りとて思想のみにては決して文芸といふこと能はざるなり、此点に於て吾人は非文学党の非文学見に同意すること能はず。先覚者は知らず、末派のポジチビズムに於て、文学をポジチーブの事業とするの余りに、清教徒の誤謬を繰返さんとするに至らんことを恐るゝなり。』
また当時の日本の文学に対しては、人間の生命の根本を愚弄するもので、彼らは愛情を描いてかいるが、それは肉情的愛情のみで、プラトン、ダンテ、バイロンなどが表現する恋愛とは別物だとする。また節義や善悪を説いていても、それは人形を並べているようなもので、人間の根本に生命の絃に触れるものではないと痛烈に批判する。透谷はドスト・エフスキーの「罪と罰」についても論文を書いているから、日本文学の概念にはなかった、人間の原罪、それとの葛藤といったテーマで書かれている西洋の文学に比べて当時の日本文学に対して面映ゆいものを感じ、何とかしなければという焦りのようなものを感じていることがうかがわれる。
根本の生命を伝えることが文学者の務めで、詩人や哲学者の仕事は人間の内部の生命を語ること以外にないとする。その内部生命はそれぞれの人間に固有のもので、神以外に、この内部生命を動かすことはできないと主張する。
詩人や哲学者は人間の内部生命を観察してそれを現すのだが、冷静に観察するというのではなく、内部の生命の様々な表出を表現するのでなくてはならないとする。
『詩人哲学者の高上なる事業は、実に此の内部の生命を語(セイ)るより外に、出づること能はざるなり。内部の生命は千古一様にして、神の外は之を動かすこと能はざるなり、詩人哲学者の為すところ豈に神の業を奪ふものならんや、彼等は内部の生命を観察する者にあらずして何ぞや(国民之友「観察論」参照)、然れども彼等が内部の生命を観察するは、沈静不動なる内部の生命を観るにあらざるなり、内部の生命の百般の表顕を観るの外に彼等が観るべき事は之なきなり、即ち人性人情の Various Manifestations を観るの外には、観るべき事は之なきなり。』
詩人、哲学者の観察眼はインスピレーションに寄るものでなくてはならない。詩人、哲学者は、人間が被造物、神から造られたものであることを信じなくてはならないと主張する。
創られたものとしての生命、ここに宗教の源泉があり、道があり、法があるとする。内部の生命」の何かを知り、インスピレーシヨンを信じる者でなくては、真の人間を観察し表現するものには成り得ないと語る。
『詩人哲学者は到底人間の内部の生命を解釈(ソルヴ)するものたるに外ならざるなり、而して人間の内部の生命なるものは、吾人之れを如何に考ふるとも、人間の自造的のものならざることを信ぜずんばあらざるなり、人間のヒユーマニチー即ち人性人情なるものが、他の動物の固有性と異なる所以の源は、即ち爰(こゝ)に存するものなるを信ぜずんばあらざるなり。生命! 此語の中にいかばかり深奥なる意味を含むよ。宗教の泉源は爰にあり、之なくして教あるはなし、之なくして道あるはなし。之なくして法あるはなし。-中略ー内部の生命あらずして、天下豈、人性人情なる者あらんや。インスピレーシヨンを信ずるものにあらずして、真正の人性人情を知るものあらんや。』
では、透谷の言うインスピレーションとは何か。
インスパイアーされた詩人こそが、真の理想家で、インスピレーションを知らない理想化はなく、宗教が何なのかを知らない理想家もない。
インスピレーションとは宇宙の精神、すなわち神によるもので、人間の内部の生命に感応するものと語り、透谷自身の感覚としては、電気を感応するようなものだと言う。
このインスピレーションが人間の生命を再造し、内部の経験と自覚を再造する。
生命の眼を以て、超自然のものを観る。そして再造された生命の眼を以て、具体的に表現したものがその極致、つまり、力を尽くして最終的に到達するところだと結論づけている。
『この感応は人間の内部の生命を再造する者なり、この感応は人間の内部の経験と内部の自覚とを再造する者なり。この感応によりて瞬時の間、人間の眼光はセンシユアル・ウオルドを離るゝなり、吾人が肉を離れ、実を忘れ、と言ひたるもの之に外ならざるなり、然れども夜遊病患者の如く「我」を忘れて立出たちいづるものにはあらざるなり、何処までも生命の眼を以て、超自然のものを観るなり。再造せられたる生命の眼を以て。
再造せられたる生命の眼を以て観る時に、造化万物何(いづ)れか極致なきものあらんや。然れども其極致は絶対的のアイデアにあらざるなり、何物にか具躰的の形を顕はしたるもの即ち其極致なり、万有的眼光には万有の中に其極致を見るなり、心理的眼光には人心の上に其極致を見るなり。』
(明治二十六年五月「文学界」24歳 )