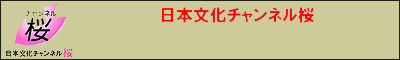目次|過去|未来
| 2009年10月17日(土) | セント・エルモの火?と山姥(やまんば) 2/2 |
→セント・エルモの火?と山姥(やまんば) 1/2
…山小屋には風呂、ウォシュレットや泡のトイレが完備され、尻が洗える所も出て来た。これも、中高年登山者、若い女の子などの入門に拍車をかける。旅行社は敏感に反応して宣伝、にわか登山パーティ参加者を募る。各人バラバラ、登山行程など、全部他人任せ。昔流行った農協ツアーのごときである。高峰登山の裏側には、困難と危険が同時にある事が忘れ去られている。
今回下山時に、三十人近くの高齢登山者の群れとすれちがった。延々、登って来る。山は登り優先だから端に寄って待機、やり過ごすのがマナーとなっている。ところが流れが切れない。ちょうど真ん中辺りをやり過ごした時、ガイドと思しき人が、「まだあと十数人来ます。すいません。」といって登って行った。別に急ぐわけでもなかったので待機した。初老の女の人のどよんとした目、くもった表情、全然楽しそうではない。何でこんなつらい事をしてまで団体の流れの中にいるのだろうと不思議でしょうがなかった。
一方、年若い連中とのすれ違い様の、
「ちーっす」「有り難うございま〜す」
苦しそうな中でも、目が生き生きして喘いでいても何か楽しさが溢れていた。
思うに、先の大団体は甘い言葉にのせられ、初めてやって来た人が多かったのではないか。これでは、一旦緩急あれば遭難へと一直線につながる。簡単に遭難してしまう一端を見た気がした。
山に来ようなんて高齢者は大体金銭面で困っている人はいないだろうから、旅行社が募った団体で登るなどとケチな事をせずに、個人、又は少人数で山岳ガイドを雇えばいい。そんな金はないと言うんだったら、三千メートルは諦めて、近所のポンポコ山で我慢する。楽して(高度を)稼ぐな。ガイド代など命と他人への迷惑をかける事を考えれば、たかが知れている。
かって、横尾のテント地で、世界三大北壁を登った*長谷川恒男が目の前のテントにいた。普段は絵描きと同じで金がないから、ガイドをしているようだった。ガイドを雇うとこういう達人に案内してもらえるかもしれない。二・三人のパーティなら、ほぼ完全に手取り足取り面倒を見てくれる。山でけちるな。先の映画の測量官達だって、地場の山をよく知った案内無しでは不可能だった。
山で山小屋の厄介になり始めたのは、ここ十年くらいでそれまではテント食料を背負って行っていた。少しの金銭的余裕と、山へ行くのが自分の中でスポーツでなくなってからは、月見をしたり、沢で行ける所まで言って、酒飲んで昼寝をする。黄昏れて来る頃、山小屋に帰る。別に頂上は目指さない。ただ、山懐にいる。それは大抵、山小屋が店じまいする晩秋の頃が多かった。
今回、面白い出会いがあった。登っている途中小屋直前の雪渓の手前で、一休みしていたら話しかけて来た中年カップルがいた。こちらと同じように、初めての人を連れてきたらしいのだが、こちらの亀ののろい的山歩きと違い、一挙に上高地涸沢と登って来たらしく、その初めての人は足を痛めていた。それで山小屋の個室の状況などを尋ねて来た。
話しの中で、その男の人は整体?の先生を東京でしているらしく、評論家の*西尾幹二さんも生徒さんだったと聞いて、こちらは数いる評論家の中で、結構な愛読者だったから驚いた。大勢いる登山者の中でなんで、自分達を選んで話しかけて来たか。ただただ不思議であった。そんな話をしても西尾さんの事を知らなければ話は弾まなかったに違いない。
小屋を利用し始めて困った事があった。
部屋が暑すぎると言う事だった。
涸沢は七月末で夜は五度位。ところが密閉度の高い高地の山小屋の個室は、冬でも甚平で過ごす身にとっては暑くて眠れない。今回も同様で、深夜二時頃、窓を開けて真っ暗な奥穂に詰め上がる雪渓をみていた。そこで不思議なものを見た。
月はすでになく、眼下、300メートル位向こうにある涸沢ヒュッテのシルエットが薄闇の中、うすぼんやりと裸電球の弱々しい光に照らされ見えた。辺りを照らし出す程の光量はない。
そこから、何気なく山にせりあがる雪渓の上方数百メートルに目をやった。雪の斜面にぼんやりオレンジの光がともっている。
あれっ? 深夜二時である。テント地よりは随分上で、そこにテントは張れない。人が遊びに行く場所でもない。なんだろう。もう一度、涸沢ヒュッテに目をやって、再びその光った場所に目をやった時にはすでに無かった。最初にヒュッテのうすらぼんやりした電灯を見たのが残像に残って雪面に投影されたのだろうか。そう思って何度か試してみたが同じようには見えなかった。
翌朝、同じ辺りを見たが何もなかった。あれは何だったのだろう…。
ここ数年、若き山女(やまじょ…山に行く女)が増えたと新聞に書いてあったので、それとなく観察して歩いた。確かに若い女の子が、一人で来ているのをまま見かけたが、全体に若い人は少なく、どちらかというと山姥(やまんば)が多く跋扈していた。昔、老婆は山に捨てられたが、今は自分から出向き、なんと!帰還する。遭難する事を考えたらそれはそれで、めでたい…か。
*セント・エルモの火…正確には、悪天候時に静電気などが尖った物体に発生させる、青白いコロナ放電による発光現象。尖ったものは無かったので球電(赤から黄色の暖色系の光を放つものが多い。自然発生したプラズマのかたまり。空中を浮遊する)の方に近いかもしれないが、浮遊はしていない。
*長谷川恒男…冬季未踏であった谷川岳一ノ倉沢滝沢第2スラブを単独初登攀。ヨーロッパアルプスの3大北壁(アイガー、グランド・ジョラス、マッターホルン)の冬期単独初登攀の成功は世界初。1991年、パキスタンの未踏峰(当時)ウルタル II峰で雪崩に巻き込まれ星野清隆と共に遭難。
たん譚はかって各3大北壁の下で昼から酒飲んで酔っぱらっていた事がある。目(未)登峰
*西尾幹二…日本のドイツ文学者、評論家。ニーチェの研究家。「新しい歴史教科書をつくる会」の初代会長
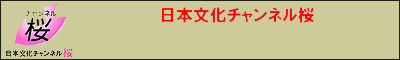
| 2009年10月09日(金) | セント・エルモの火?と山姥(やまんば) 1/2 |
7月の末から八月の初め頃、北アルプス北穂高直下の涸沢小屋にいた。友人の遅い山入門の先達として同行した。この時期、涸沢から下は雪があったとしてもごくわずかで、簡易アイゼンを付けたり、山小屋の従業員が階段を切ったりするほどの残雪は無いのが普通で、小屋につくまでにアイゼンを効かせて登るなどというのはついぞ無いことだった。
この時すでに上高地界隈で行方不明者一人の捜索願が出ていた。また高齢者である。
巷、山岳ガイド地図が売られている。友人にはそれを持ってくるように言って、それで読図してもらおうと思った。が、この「大きなお世話」地図は、どこが危ないとか、鎖場だとか詳しく書き込みはあるが、実際に山の形を読んであの山がどれだとは言えない作りになっている。書き込みが多すぎて等高線が読めない。したがって、読図が出来ない山地図である事に改めて気づいた。
これを見て、初心者がわかったつもりで入山して、山行く人につられて難度を考えずに岩場に入って遭難する。最近も、奥穂高ジャンダルム辺りで動けなくなって、ヘリコプターが救出に向かったが、尾翼を岩に当て墜落、当人と四人が亡くなっている。
中年を過ぎて山入門をし夢中になる。が、感性は豊かでも体力は確実に衰えている、若い頃から山に親しんで自分を知っていれば非常事態に際して勘は働く。これは大雪山の遭難でもあったように、生死の分かれ目になる。
夜、月を見ながら小屋前デッキで友人と飲んでいると、初老が話しかけて来て、「明日は北穂高から涸沢岳、奥穂とやってここに帰って来るがどうだろう」と言うので、山歴を聞いたら初めてだと言う。こちらは心底驚いた。
例へ同行している友人が行きたいと言っても連れては行かない。はっきりいって考え無しの無謀である。やんわりと無茶ですと言って断念させた。多分こういう人が一杯いるのだろう。
登山はスポーツではない。sportは「気晴らしをする、遊ぶ、楽しむ」が元々の意味だが、さらに語源的に云うと古仏語のportare「荷を担ぐ」の否定形から、desport「荷を担わない、働かない」となって上のSportの意味となった。しかし山の基本は「荷を担ぐ」んである。苦痛を伴うものなのである。そういう意味でもスポーツではないし、現在のスポーツの大半を占める勝敗を競うものでもない。
山は昔、修験者の場であった。映画、剣岳「点の記」で西洋かぶれの*小島烏水が日本で初めて山岳会を作り、勝手に国家大事の測量官達に対抗意識を燃やして剣岳初登頂を目指す。日本人としての目で西洋を見た最期の人と言われた夏目漱石と同様の目を持った測量官達の、
「何のためにただ頂上を目指すんだ?我々が頂を目指すのは仕事のためで、そこから仕事が始まるのだ」
という疑問の言葉は、まさに昔の日本人が持っていた山(自然)に対する感覚だった。
登山(アルピニズム)は英国発祥で、「勇気」を試され征服欲を満たす。アングロサクソンの持つ特徴とも思える。より困難でより高度な頂への挑戦。もともとは貴族の遊びだった。一方、 同じ英国の中でもウエールズ・スコットランドなどに住むケルト民族には、その土地の特徴、規則性をもった風景を楽しむと言う考え方に基づいたピクチュアレスク(Picturesque)という概念があった。もともとそれは、英国南西部に広がるウエールズに関してのガイド本にも現れ、またそれはケルト主義を表わす本でもあったようだ。
…続く。
→セント・エルモの火?と山姥(やまんば) 2/2
*小島烏水 …日本山岳協会設立者の一人。登山家、文芸批評家、浮世絵研究家、横浜商業学校卒業後、横浜正金銀行に勤務、「文庫」記者として活躍、文芸、社会、人物批評に健筆をふるった。
烏水は明治六年生まれ、漱石は慶応三年生まれ、明治(明治元年は慶応四年)と言う時代がどれほど日本の文化的側面に影響を与えたか.善かれ悪しかれ、形を変えて両者に現れていると思う。
→2007年の今日のたん譚 -これは事件か?-