昨日の雨で寒気が流れ込んで来るのではと思っていた。
今朝は思いがけずに暖かくほっと胸を撫で下ろす。
一雨ごとに冬が深まるわけでもなさそうだ。
SNSでは未だに「秋」とつぶやく人が多く違和感を感じている。
「立冬」「小雪」となれば季節は初冬なのではないだろうか。
もちろん反論は出来ない。それが少なからずストレスになっていく。
波長の合う人と合わない人もいる。それも仕方ないことだろう。
私は極力誰とも親しくならないことを心掛けている。
言葉は悪いが「触らぬ神に祟りなし」なのかもしれない。
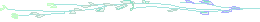
山里では2件のお葬式があった。義父が喪服を着て出掛ける。
仕事が立て込んでおり時間のロスであったが義理は欠かせない。
義父は夜なべで仕事をすると言う。それも苦にはならないようだ。
そんな義父のおかげでどれほど助かっていることだろう。
私は事務仕事以外は何も出来ない。それがもどかしくてならない。
母は整備士の資格を持っていたけれど工場で働くことはなかった。
私もそれで良いのだろうか。全く役には立たないのだけれど。
同僚にはなんと口うるさい事務員だと思われているかもしれない。
頭の中はもう12月のスケジュールでいっぱいになっている。
繁忙期をなんとしても乗り越えなければいけない。
義父や同僚には大きな負担を掛けざるに得ないだろう。
難破船は何処の海を漂っているのやら。
やがては辿り着く島があるのに違いない。
雨のち曇り。あたりをしっとりと潤すような静かな雨。
幸い気温は高めで冷たさを感じなかった。
勤労感謝の日で祝日であたっが娘夫婦は仕事に行く。
何のための祝日だろうと思うけれど
働いてくれている人達のおかげで暮らしが成り立っている。
市街地では「一条大祭」市を代表する一条神社のお祭りだった。
昔から寒さが一気に厳しくなる頃で小雪が舞った年もある。
今日は生憎の雨であったが参拝者は多かったのかもしれない。
子供の頃には親と行くよりも子供同士で行くのが習いだった。
お小遣いを貰ってバスに乗って行くのがとても楽しみであった。
今の子供はどうなのだろう。昔ほど興味が無いようにも思われる。
神社に関心が無くなり出店も楽しみではなくなっているようだ。
欲しいものはいつでも手に入る世の中になってしまっている。
我が家では仕事を終えた娘夫婦がめいちゃんだけ連れて行く。
あやちゃんは例の調子で「別に・・」とそっけない。
夕食は帰宅してから食べるそうであやちゃんは私達と一緒に食べた。
食べ終わるなりお風呂に入り今は宿題をしているようだ。
洗った髪が濡れたままだったので「また風邪を引くよ」と
声をかけたら「うん、わかった」ととても素直である。
もし一緒に暮らしていなかったら独りぼっちでいるのだろうか。
子供心に私達を頼ってくれているような気もして嬉しかった。
そろそろ娘達が帰って来る頃である。
めいちゃんは大好きな綿菓子を買って貰っただろうか。
にこにこ笑顔を待っている夜のこと。
二十四節気の「小雪」そろそろ雪が降り始める頃。
季節はもう本格的な冬と言って良いだろう。
南国土佐は暖かな一日となったけれど北国を気遣う。
もうすでに初雪が降っており厳しい寒さに見舞われていることだろう。
仕事帰りに星ヶ丘公園に立ち寄っていた。
樹々の紅葉がわずかに見られたけれどあたり一面が雀色。
竜胆も枯れ始め山茶花も散り始めていた。
葉をすっかり落とした柿の木がたわわに実を残していたのが
唯一の彩りに見えほっと心が和んだような気がする。
植物も冬支度なのだ。寒さを乗り越えてこその春なのに違いない。
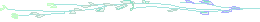
椎名誠の「ぼくがいま、死について思うこと」を読んでいるが
死を恐れる気持ちや不安な気持ちが無いことに勇気づけられる。
「悪運に強い」と記されているが正にその通りだろう。
生命力は人それぞれだと思うけれど自分の命を信じること。
これくらいのことでくたばってたまるもんかと思いたい。
幸い私はこれまでの人生で九死に一生を得たことはない。
辛いことは沢山あったけれど命に関わる事ではなかった。
少女時代に「死にたい」と思ったことはあったが
そう思う自分を憐れに思うばかりであった。
自分が可哀想でならない。けれども死んでしまえばもっと可哀想だ。
人は何があっても生きることを諦めてはいけないのだと思う。
瀬戸内寂聴は「定命が尽きるまで」と言った。
定命とは仏教の言葉でこの世に生まれた時からすでに定まっている
寿命のことである。幼い死もあれば長寿を全うすることもある。
それは誰にも知らされていない。だからこそ生きなければならない。
今日かもしれない明日かもしれない漠然とした命である。
私が死を怖れるようになったのはまだ40代の頃だった。
怖れと云うより不安でならなかった。心細くてならなかったのだ。
確かに生きているのだけれど心もとない。
これで良いのかこのままで良いのかと自問自答を繰り返すばかり。
自分がとてつもなく儚い存在に思えてならなかった。
今思えばそれはとても愚かなことだったのかもしれない。
とにかく与えられた一日を全うすること。
今は精一杯に生きているのだと自分を信じている。
小春日和が続いていると急に冬将軍がやって来そうな気がする。
私はまだ寒さを怖れているのだろうか。自分でもよく分からない。
覚悟はしているつもりだけれど少し臆病になっているようだ。
ご近所の奥さんから頂いていたコキアがすっかり枯れてしまった。
「枯れたら捨ててね」と言われていたのだけれど
潔くそれが出来ずに未だに玄関先に置いたままだった。
根があるのだから春になったら新芽が出るのかもしれないとか
来年の秋には紅葉するかもしれないとか未練がましく思っている。
たぶん私は捨てない。ささやかな希望を持ち続けていたい。
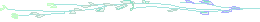
土曜日曜と二日続けて母から電話があった。
ちょうど私がこの日記を書いている時のこと。
着信履歴を見て私が掛けていたと思い違いをしたようだった。
「それは先週の事やろ」と言ったら「ありゃそうかね」と応え
「私って呆けちゃったのかしら」とひょうきんな声を発する。
介護士さんに屋上へ連れて行って貰ったのがよほど嬉しかったらしく
二日続けて同じ話をする。「昨日も聴いたけん」とつい言ってしまった。
すぐにしまったと思ったけれどもう後の祭りである。
何度でも耳を傾けてあげるべきだったと深く反省をした。
土曜日曜はリハビリも休みで介護士さんも最小限のようだった。
母にとっては誰もかまってくれない寂しい週末だったのだろう。
訊きもしないのに「ご飯が美味しい」「なんと幸せ」と言う。
それが少し切なかった。まるで寂しさを胡麻化しているよう。
母は沢山の人に囲まれていてもどうしようもなく孤独なのだと思う。
私は薄情な娘のままだった。今も母からの電話を待ってはいない。
ただ母を捨てることは決して無いと思う。
日中は曇りの予報だったけれど思いがけずに晴天となる。
気温も20℃を越えずいぶんと暖かくなった。
初冬の陽射しのなんと有難いことだろう。
朝陽が射し始めた頃にお大師堂へ。
お堂に続く小径には枯れ葉がたくさん舞い落ちていた。
踏みしめながら歩くのがなんとも心地よい。
川岸では魚釣りをしている人がいた。
のどかな朝の風景にこころが和む。
花枝(しきび)が気になっていたので持参して行って良かった。
葉がずいぶんと落ちておりもう限界だったようだ。
誰かが菊の花を添えてくれていた。
お参り仲間さんの心遣いが嬉しくてならない。
手水鉢の水が空っぽになっており残念でならなかったけれど
足の痛みがあり川の水を汲みに行けなかった。
誰かが汲んで来てくれるだろうと前回にもそう思ったことだった。
人を頼りにしてはいけないのだなとつくづく思う。
私も「出来ない」と決めつけているのかもしれない。
川のせせらぎの音を聴きながら般若心経を唱えた。
最後には願い事ばかりでお大師さんに申し訳ない。
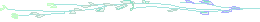
10時頃からプチドライブ。真っ青な海を眺めながら四万十町まで。
お目当ては例の行列の出来るラーメン屋さんであったけれど
駐車場は満車状態で仕方なく諦めざるを得なかった。
町中まで戻り国道沿いのお食事処のお店に入った。
初めてであったが落ち着いた雰囲気の庭がありこれは良いなと思う。
紅葉した木の根元にふくろうの置物がありとても可愛かった。
他のお客さんは皆ラーメンを食べており美味しそう。
私達も迷わずにラーメンセットを注文する。
混んでいるにも関わらず10分で運ばれてきて驚いた。
スープは少し濃い目。麺は程よい柔らかさ。
もやしは入っていなかったがたっぷりの葱とチャーシュー。
チャーハンには紅生姜がトッピングされていた。
「満足、満足」夫と二人お腹を撫でたのは言うまでもない。
行列の出来る店に拘らなくても穴場が確かに在ったのだった。
「また来ようね」と笑顔で帰路に就く。
私は凄く眠くなってしまってこっくりこっくりしながら
時々はっとしたように真っ青な海を眺めていた。
曇り日。時おり霧のような雨が降る。
朝は晴れていたので大量の洗濯物を干していた。
すぐに取り入れ乾燥機のお世話になる。
以前はよくコインランドリーに行っていたけれど
ずいぶんと便利な世の中になったものだ。
子供たちが赤ん坊の頃には布おむつが乾かない時
一枚一枚アイロンを掛けていたことを思い出す。
午前中に図書館とカーブス。
図書館では椎名誠のエッセイ本を2冊借りて来た。
椎名誠の本を読むのは20年ぶり位ではないだろうか。
とにかく懐かしい。まるで古い友人に再会したようだ。
カーブスでは知り合いのお仲間さんに久しぶりに会えて嬉しい。
憂鬱な気持ちは何処へやら。おかげで今日はとても楽しかった。
やはり気の持ちようなのだとつくづく思ったりする。
コーチの励ましにも素直に頷いている自分がいた。
笑顔は大切。きっと心も微笑んでいたのだろう。
午後は炬燵に潜り込みひたすら怠惰に過ごす。
孫達の昼食は娘が用意して行っていたのでとても助かった。
お昼に声を掛けたら「勝手に食べるけん」とあやちゃんが言う。
本当に手が掛からなくなった。それがちょっぴり寂しい。
夕飯は娘が牡蠣フライを揚げてくれて私は肉じゃかとオムライスを作る。
娘婿が珍しく早くに帰宅していたけれど一緒に食べることはしない。
もうそれが当たり前の日常になりずいぶんと経った。
先に夫と二人でさっさと食べる。会話も殆どしないことが多い。
食べ終わるとすぐに席を立ち娘たちに食卓を譲るのだった。
それも慣れてしまうと気にもならず当然のことになっていく。
「家族団らん」には程遠い暮らしだけれど寂しさは感じない。
娘たちの楽しそうな声を聴くだけで幸せだなと思うのだった。
朝の寒さもつかのま。日中は小春日和となる。
寒暖差にもすっかり慣れて来たようだ。
芒の穂がずいぶんと白くなって来た。
人間だと70歳位だろうか。老いを感じる頃である。
それでも陽射しを浴びてきらきらと輝いている。
嘆くことなど何ひとつないのだろう。
やがては枯れることも怖れてはいないのだ。
そんなふうに生きられたらどんなに良いだろうか。
私も野に在りたい。そうして命を全うしたいと思った。
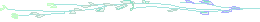
工場にみい太の子供であると思われる子猫がやって来た。
先日見かけた時よりも少し大きくなっている。
さほど瘦せ細ってはおらず元気な足取りにほっとしたけれど
いったい何を食べて暮らしているのかと気掛かりでならない。
子猫を見つけた義父が突然石を投げ始めて驚く。
そこまでしないでもと思ったけれど何も言えなかった。
子猫は一目散に逃げて行ったがその後姿のなんと憐れなこと。
義父にしてみれば工場を猫だらけにするわけにはいかないのだろう。
みい太は仕方ないとしても子猫の面倒まで見る気はないのだ。
心を鬼にしているのがわかるだけにとても複雑な気持ちになった。
山里には「猫屋敷」と呼ばれている民家がある。
ざっと数えただけでも10匹は居るのではないだろうか。
その民家の主は生活保護を受けていると聞いたことがある。
自分の暮らしもままならないのに猫達と暮らしているのだった。
身を削っても猫達に愛情を注ぎ続けているのだろう。
陰口を叩く人もいるらしいが全く気にしていないようだった。
たとえ猫でも尊い命には変わりないのだと思う。
義父はこれからも石を投げ続けるのだろうか。
私は出来ることならばそんな義父の姿を二度と見たくないと思う。
|