夕暮間近。茜色の真っ只中にあり家路をいそぐ。
ずいぶんと枯れてしまった尾花のことをふと愛しく思う頃とて。
彼女には彼女なりの生き様があるのを目の当たりにしてみると。
すこしも儚さを感じず。むしろこれほどにも強くと心を動かされるのだった。
落日に立ち向かう。その言葉に『年頃』をつけると。ちょうど私の頃に似て。
これまでどんなにかその頃を怖れていたことだろうか。急いて焦って転んで。
きっとものすごく不安だったに違いない。時がひしひしと迫って来るその影から。
もがいては逃げようと逆らうことばかり考えていたのかもしれない。けれども。
いまは。すこし違う。なんだかもうすっかり観念してしまうとただただほっと。
いくぶんその渦の流れに身を任せられるようになったような気がするのだった。
もうじゅうぶんなのかもしれない。なんとなくこのうえなど望まぬような心が。
私を救ってくれているように思う。あとはただ精一杯でいるだけでよいと思える。
ひとと出会い。それをかけがえのないことに思い。そのひとの心のつかの間にせよ。
私と云う名の『ひと』が息づいていられたらと。ただただそれだけを願っている。
私は記したいのだ。そのひとの人生の一部でいい。私と云う存在を残しておきたい。
ついつい思い詰めてしまうこともあるけれど。それは忘れられる事の辛さかもしれない。
だけど。そんな辛さにばかり拘ってなどいられない。
私は立ち向かっていく。落日の向こうにはきっと明日があるのだから。
真っ青な空に。北風がひゅんひゅん。縁側でぽかんとしつつ日向ぼっこもよいもの。
ノースポールの花は寒さに強いのか。白い花びらにレモン色の口元を似合わせて咲き。
たくさんの蕾が希望みたいにふくらんでいるのが。いまはわくわくと嬉しくてならない。
愛でてほめて育てる喜びというものだろうか。植物と身近に暮らせるのは幸せなことだ。
慰めてくれて心和ませてくれて。だからこそ粗末には出来ず一入の想いが募るものである。
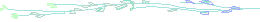
昨夜から決めていたことで。今日は髪を切りに行った。
中途半端なのじゃなんだか嫌で。とうとう夏のように思い切りよく切った。
最近ますます太り気味のまんまるな顔の上に。かろうじて髪が載っているような。
家に帰るなり手を叩いて笑われたけれど。私はとても気に入っているので微笑む。
生き返ったような気持ち。すかっと爽やかな気持ちでいる。
ちょっとやそっとではへこたれないぞ!と我ながらすごく勇ましい姿になった。
| 2006年12月09日(土) |
あてもなく流れるようにいま |
曇り日の空から。やがて絹のようにやわらかな雨が降り始めた午後。
炬燵にもぐりこんではひたすら眠る。猫のようにまあるくなって眠る。
夕方にはしぶしぶと起きたものの。買物に行くのも億劫でならず。
昨夜の残り物や。冷蔵庫の中をあさるようにしてしごく質素な夕食とする。
昔はね配給だったんだよ。お芋さんが主食だったんだよとか言いながら。
そうかそうかと頷くひとと差し向かえば。蕪の浅漬けもご馳走となるもの。
そうしてすっかり夜になると。お風呂ほど楽しみなものはなく。ぽかんと。
なにもかもとろけそうな気持ちを擦るようにお湯の中で腕を膝を指までも。
あたたかくする。ふと目を閉じて想うこともなんだか幻のような儚さである。
そうして。サチコが帰り着く時まで。自室に閉じこもってはひたすら待つ。
なんだか雨に濡れそぼった庭の雑草のようで。陽の光を恋しがるように。
『いちむじん』のギターの音色を聴きながら。あてもなく流れるようにいま。
戯れに言葉を綴りつつ。きもちよく心地良く流れ着きたいものだと思っている。
ととっとんと。音色と音色のつかの間にその指でギターを叩く音がとても好きだ。
ものすごくそこにあるひとの息を感じる。はっとするほどその存在がありがたい。
なんだかこのまま。ふかいふかいところに行ってしまいそうだ・・・。
サチコの声がきこえたら。駆け足で帰って来よう。
そしてちょっとふざけあって笑おう。
朝から絶え間なく雨が降る。不思議と鬱陶しくもなくむしろ心地良い雨の音。
気分がとろとろっとしている。なんだか腑抜けていて。なんだか柔らかくて。
仕事の合い間に手紙を書いた。走り書きだけれど心を込めて書いた。
自分はきっと。そのひとにとってなくてはならない存在ではないと。
いまは思う。差し出がましく厚かましくすごいおせっかいに違いない。
だけどこの縁だけはどうしても切れない。漠然とそう確信しているところがある。
いつだってそれは私の『感』に他ならず。理由というものがなく直向に行きたがるのだ。
不甲斐ない我が身はひとを救うことが出来ない。その出来ないを何度射されようと。
もしかしたらと一縷の望みを捨てる事が出来ないのだった。ながいことどんなに遠くても。
届けられるものを私は持ち続けたいと思う。命ある限りそれを貫いて生きたい。
たぶん初霜ではないと思うのだけど。私には初霜だった朝のこと。
いつもの峠道を越えて。あたりが山里に差し掛かる道沿いにあって。
そこは秋の日までは広いオクラ畑だったのが。今ではブロッコリー畑。
粉砂糖をまぶしたように見える。その緑の原の白く装ったのを見たのだった。
そして道行けば。雀色の丘さえもきらきらと眩しくてまるで別世界のようす。
ここが冬なのか。冬もなかなかによいものだなと思う。まだほんの始まりのことを。
しみじみと思った。懐かしいようでもある。そしてすこし切ないようでもあった。
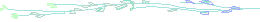
仕事で。お客さんのお宅までバッテリーの配達に行った。
クルマのエンジンが掛からないので。はるばる自転車で買いに来てくれたのに。
ちょうど在庫が切れていてとても申し訳がなく。とにかく後から届けることにした。
「自転車はよいよ冷やかった。向かい風やったけん」と毛糸の帽子を被ったおじさん。
山里のこんな田舎だからこそ。すぐに間に合わせてあげなくてはいけないものを。
なくても当たり前だと咎めもしないのは。のんびり気質のおおらかさであろうか。
ついつい焦りがちになる私などには。ほんとうにこれほどありがたいことはない。
おじさんの書いてくれた地図を頼りに行く。そしたらおじさんが道路まで出てくれていて。
ずっと待っていてくれたらしい。「すまんのぅ」って言ってくれて。それはこちらこそで。
手渡すなり「ねえちゃんちょっと待ってや」って言って。すぐそばの木の枝に手を伸ばす。
そこには白とピンクの彩りの小さな可愛らしい籠がぶら下っていたのだった。
おじさんのお手製らしい。「これあげるけんね」って。すごくすごく嬉しかった。
木枯らしもなんのその。今日もとてもあたたかい「ひと」に逢えました。
いちだんの寒さには。まだそのうえ。まだもっとそのうえの寒さが来るのだけれど。
なんだか早くもからだがぎこちなくなり。空を仰ぐことさえも臆病になってしまう。
昨夕は軒下のシャコバサボテンを抱えて。とうとうこれも居間で冬ごもりとなった。
白いのと薄桃色とふっくらと蕾をつけて。クリスマスの頃には満開になることだろう。
植物はみな等しく愛しいものだけれど。冬の頃に咲いてくれる花はとてもありがたいものだ。
さて。ところでと。なんだか感慨に浸っているのはほかでもないけれど。
今日で私もとうとう観念すべきほどの歳となった。ほんとうにもう引き返せない。
とにかく進むしかないのだと思うと。今更咲けもせずかといってまだ散れもせず。
ましては枯れる訳にもいかぬと。心の奥深いところから何かが込みあげてきたりする。
不思議であり奇妙でもある。これまでの生き様など思うと映像のようにも浮かぶのだけれど。
何がよかったとかあれが悪かったとか。ここまで来るとすべてがきっかけとなって。
転がるように流れるようにずっとずっと続いてきた道のように思えてくるのだった。
出逢ったひとたち。時には私を戒めてくれたひと。優しく労わってくれたひと。
そしてそっと背中を押してくれたひと。また強く突き放してもくれたひと。
抱きしめてくれたひと。寄り添ってくれたひと。こころから愛してくれたひと。
一期一会が身に沁みる。ほんとうにありがたい出逢いを重ねる事が出来たのだった。
まだまだ生きる。まだまだ歩く。はるかかなたでまたきっと出逢うために。
12月の声を聞くと。やはりさすがに冬らしく。南国とはいえきりっとした寒さ。
青空にほっとしていてもたちまちのうちに暗雲が広がり。強い風と共に時雨も来る。
早朝。彼とふたり川仕事に出掛けた。ちょうど朝陽が昇り始めた頃の紅い空は。
なんともいえず美しい空で。月ではないかと思うほどの太陽はその輪郭も鮮やかに。
くっきりと燃え始める前の光のかたちを見せて。終わりではなく歩むことを知らせてくれる。
堤防から見下ろす川海苔の漁場は。これもまた感嘆の声をあげずにはいられなくして。
カメラ持って来ればよかったなあって彼が言ってくれたのが。やたらと嬉しかったりした。
今年も海苔の生育は順調で何よりに思う。年明けからすぐに収獲出来そうで胸が膨らむ。
自然の恩恵を受けられることは。ほんとうにありがたいことだとつくづく思うのだった。
午後。急に思い立ち。和室の障子を張り替えてみようと決める。
昨夜見たテレビ。 三丁目の夕日の影響かもしれなかった。
障子を破いてみたかった。拳骨でバシッバシっとそうしてベリベリっと剥がしてみたい。
うん。そうそう。子供の頃にはこれが楽しみだったと思い出しては懐かしくてたまらない。
水の冷たさもなんのその。この爽快に勝るものはないと思える。ほんとにいい気持ちだった。
だけど。それからすぐに時雨が来て大慌てで。まだ乾き切れぬのを座敷に立てかけては。
ふうはあの溜息がどっと出て来る。破くのは楽しいけれど張るのはいささか憂鬱なものである。
それはひとりではとうてい無理であると決め付けて。とうとう彼の手を借りることになった。
彼はさすがに手際よく。それも遠い昔を思い出しているかのような微笑ましい姿で。
下から順番に張るんだぞとか言いながら。近視の眼鏡をはずして目を細めての作業であった。
そしてもう夕暮近く。おおっと声をあげるほど綺麗にすべての障子を張り替えてくれたのだ。
真新しいその和紙の白さほど暖かなものはなく。なんだか胸に込みあげてくるような空気に。
満たされていて。ほのぼのと幸せだなと思う。彼にそっと手を合わしたい気持ちだった。
思えば。今までずっと。破り続けていたのは わたし。
彼といういうひとは。なんどもなんどもそれを繕ってくれたひとだったのだ・・。
|