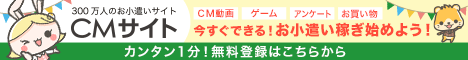| 1981年10月06日(火) |
ブラック・コーヒー。 |
ブラック・コーヒー
「甘々のミルクコーヒーが好きじゃなかったっけ」
テーブルに置かれている二つのコーヒーの色が同じな事になんとなく違和感を感じて、そう呟いた。
「…変わったの」
少しの間をおいてからの答えには、どこか、「つっこんでくんなよ」という匂いが感じられる。
視線を泳がせる松本。そう、そこを逃しては、面白くない。
「へぇ?」
「…なんですか」
案の定、口調が変わった。それと同時に甦る記憶がひとつ。
「いや別に。そういえば随分前に、なんかそういう宣言されたなぁって思い出しまして」
自分でも意地の悪い言い方だと思った。
松本の顔から、さっと血の気が引くのがわかる。
思い出されたくないんだろう。数年前の堂々と全身から「翔くんスキ」光線を出していた自分を。
そんな様子が面白くて、どうやっていじめてやろうかな。
なんて事を考えながらカップをソーサーに置くと、チン、と、小気味の良い音がした。
あれは何年前のことだっただろうか。
今と同じ、いや、控え室だか…ホテルのラウンジだか…どこだったかなんて忘れてしまったけど。
あの時もそう、ふたりでコーヒーを飲んでいた。
「翔くん、砂糖入れないの?」
透明の小瓶から角砂糖を取ってから、松本は小首をかしげてそう自分に聞いてきた。
「あ、俺、ブラック」
片手で軽くそれを制止して、真っ黒なコーヒーを一口飲む。
「うそー。すっげぇ」
「何が」
感動したように俺とコーヒーカップを行き来する松本の視線を、正直うざったいと思った。
「ブラックコーヒーって、なんかオットナーなイメージ」
瞳をきらめかせる松本。
アホ臭い。コーヒーごときでオトナもコドモもあるか。
そう言いたくなったが、そんな自分も相当子供だと思い直し、無言でコーヒーを啜った。
読んでいた雑誌に視線を落とし、まだ此方の様子を伺ってる松本には気付かないフリをする。
「苦くない?」
「オトナだね」
そんな言葉を繰り返している松本の足を、軽く蹴った。
「うるせぇよ」
一瞥すると、やっと静かになる。
と、途端松本はわざとらしく頬を膨らませて、無言で真っ黒のままのコーヒーを一気飲みした。
あまりに唐突な行動に、その姿から目が放せない。
最後の一滴まで飲み干してから、松本は嬉しそうに空のコーヒーカップを掲げて微笑んだ。
「翔くんの真似」
その行動と発言に確実にひいたことだけは覚えている。
が、まさかその「真似」を今でも継続していたとは、思いもよらない事実だった。
そういえばあれ以来、松本はコーヒーを飲む時いつも言っていたかもしれない。
「これがオトナの味ってヤツ?」
「翔くんに一歩近づけた気がする」
嬉々とした声をあげながら苦そうにブラックコーヒーを啜る松本を思い出すだけで、肩が震えた。
今の松本からでは想像も出来ないくらいに粋なことをしてくれたではないか。
「成長したねぇ」
今、目の前でブラックコーヒーを飲んでるのは誰なのだろう。
あの日の可愛かった…そして少しうざったい位に自分を慕っていた松本は、もういないけれど。
何も変わっていない。自分も、こいつも。
「るせーよ」
少しバツが悪そうに悪態をつくその姿も、今は余裕で受け止められる。
最初は正直戸惑った。あまりの成長の速度に。
けれどそう、思い返してみれば、何も変わってなかった。自分と松本の関係は、何も。
成長したのは自分か?
ふっと自嘲の笑みを浮かべて、自分と松本の間に置かれている角砂糖の小瓶に手を伸ばした。
「じゃぁオレも、松本の真似しようかな」
は?と松本が目を見開いた瞬間。
「潤くん、砂糖入れないの?」
スプーンに角砂糖をのせて、わざとらしいくらい甘い瞳で見つめ返してやる。
勿論、あの時松本がしたように、小首をかしげるというオプション付きで。
松本は一瞬かっと顔を赤くして、目を逸らした。
「ホント、むかつく人だよね」
頭がこんがらがって、いつもみたいな毒が返せないことも知っている。
オレは小さく笑って、松本が控えめに差し出したカップに角砂糖をひとつ、落とした。
甘い甘い、ブラックコーヒー。
| 1981年10月05日(月) |
どんなことばで***幸せ系結末ver. |
薄暗い公園に全力疾走で駆け込むと、勝手に自分を待っているその傍迷惑な奴の姿は、すぐに目に付いた。
低いレンガの塀に浅く腰かけ、ただ空を見上げている。
数メートル手前で足を緩めると、相手もこちらに気づき、塀から腰を上げた。
「ちょーブサイクな顔」
「お前、な、人が死ぬほど、急いできたのに、第一声が、それかよ」
両手を膝について肩で息をしながらも、松本の相変わらずの悪態に一応のパンチを入れる。
が、松本は知ったことかというように、遠くを見つめながら呟いた。
「勝手にホモにしないでくれる」
「は?」
櫻井が顔を上げると、松本は両手を伸ばして空に向かって吠えるように叫んだ。
「愛してるから捨てないで〜」
数日前、櫻井が伝言係・大野に託した言葉。相当感情を込めて伝えてくれたらしい。
粋なんだか余計なお世話なんだかわからない。
「バカ、あの愛してるは」
「わかってんよ」
誤解などするわけがないだろうが、一応のフォローを入れようとすると、松本に遮られた。
それでも言葉を繋ぐと。
「親愛の愛。だろ」
ふたり同時に重なった、声。
声のトーン、一瞬あけた間すらも一緒で、お互いびっくりしたように目を合わせてから、笑った。
「敬愛でも可」
櫻井流に口を縦に歪めて、得意げに言う。勿論、右手親指アップで。
「心にもないことを」
くっくっと笑う松本。
その笑顔を見て、櫻井は小さく息を吐いた。事態はそう悪く進んでいないようだった。
「あーあ、昔はあんなに可愛かったのにな。翔くん翔くんって」
視線を落として、軽く足を遊ばせながら言うと、松本は口を尖らせた。
「昔の話」
「ほんと、昔の話。今の潤くんは思春期真っ盛りで、全然わかりません」
冗談ぽく顔を覗き込むと、松本の表情が暗くなっているのがわかった。
笑顔を期待したわけではなかったが、ここでの松本の変化に、櫻井の心に少し、緊張が走る。
少しの間を置いてから、息を吸い込んで松本が口を開いた。
「こないだは、うそついた。…嫉妬、してた。…多分。裕貴くんに」
ゆっくり言葉を繋いでいく松本。
櫻井はじっと待つしかなかった。どう、なのか。その話は、どう、進むのか。
「裕貴くんは、俺の知らない翔くんを沢山知ってるんだよな。って」
松本は櫻井と視線を合わせようとはしない。
ただ、ロングコートのポケットに手を突っ込んだまま、間を置きながら言葉を繋げた。
「俺に…っていうか、メンバーに言えないこととか、いっぱい話してんだよな。とか」
松本の言葉を噛み締めながら、櫻井の心に、また少し安堵の感が戻ってきた。
と同時に、なんだか松本がとても幼く見え、こんなのに振り回されている自分がおかしく思えてくる。
口元が緩むのがわかったが、堪え、一生懸命話してくれている松本の瞳をじっと追った。
「なんか、いきなり悔しくなっただけ」
松本も櫻井のその様子に気付いたのか、少しバツが悪そうに半ば無理矢理に話を完結させた。
それから一息ついて、やっと決心したように視線を絡ませると、トドメの台詞を吐いた。
「俺、翔くん、好きだし」
絡み合う視線。ただ沈黙が落ちる。その空気は、数日前のそれとは全く異質だが。
「なんか言えよ」
先に沈黙に耐え切れなくなったのは松本だった。
櫻井は、その様子を楽しむかのように、わざと意地悪く顎を上げる。
「お前が呼び出したんだろ」
「っ!…むっかつく」
かっと顔を赤くした松本が地団太を踏む。もう、面白くて仕方が無い。
「ウソウソ。俺も好きよ。愛してるってば」
足取り軽く松本に近寄り、肩に腕を回した。松本は顔を背けるが、その腕を振り払おうとはしない。
「もういい」
口を尖らせて反対方向を向く松本の耳が赤くなっているのを見て、櫻井はまた、顔が緩むのがわかった。
「嬉しいよ。久しぶりだし、そういうの」
わざと大きく松本に寄りかかってみせる。
本心の言葉だが、冗談めかしてしまうのは、今まで相当松本に苦しめられたお返しでもある。
「もういいって。マジむかつく」
やっと松本が、逃げるように櫻井の腕を肩から外す。
それから踵を返すと出口に向かって歩き出したので、櫻井も慌てて後を追った。
今なら、なんでも言える気がした。
あの時の質問の先にある、その真意がなんであろうと、今、今しかその答えを言う事はできないと思った。
松本の横につくと、櫻井はそのまま松本の顔は見ずに、視線は合わせずに、口を開く。
「ほんと、ほんとに。お前は俺の、オンリーワン…だし」
オンリーワンの部分だけ、ひとつ声のトーンを落として言う。意図的じゃなく、自然にそうなった。
瞬間、松本の表情がほんの一瞬暗くなったことには気付かなかったが。
いや、気付かないフリをしたかったのかもしれない。
その空気だけは、なんとなく、読み取れたから。
だが、櫻井にその空気の変化を悟らせ・理解させる間を与えなくしたのは、松本の方だった。
「返し忘れてた、指輪」
松本は思い出したように立ち止まり、ポケットから例の忘れ物…シルバーの指輪を取り出した。
手を伸ばして、櫻井の前に差し出す。
櫻井は一瞬それを受け取ろうと右手を出しかけたが、ふと思い直してその手をポケットに戻した。
もう、なんだかどうでも良くなってしまった。
「良いよ、もう。お前持ってろ」
松本の表情が驚きの色に変わる。
大して大事な物でもないしと付け加える前に、指輪を顔の横でちらつかせて松本がニヤリと笑った。
「エンゲ〜ジリング?」
さっきのお返しと言わんばかりのその黒い笑みに、櫻井は気を失いそうになる。
「やっぱ返せ」
「やだよ」
リングを取り上げようと手を伸ばすと、松本は両手でしっかりとそれを包んでしまう。
それから、既に顔を出していた月の光に反射させるようにリングを掲げて、微笑んだ。
「死ぬまで持ってる」
その笑顔と発言に凍りついた櫻井の横をすり抜け、公園の出口に向かって歩き始める松本。
とんでもねぇプレゼントをしちまった…と、白いため息を吐いて、櫻井も松本に続いて、歩き出した。
横に並ぶと、意味も無く松本の頭をぽんと叩く。
「死んでも持ってろ」
我ながら、人生で最高に恥ずかしい言葉を吐いてしまった気がする。
そう思いながらも、不思議と櫻井に羞恥の感はなかった。
松本が一瞬小さく顎をひいたのと、長い前髪に隠れた瞳が、ほんの少し、嬉しそうに細められたのが見えたから。
end.
後書き。
ギャー!!甘い!甘すぎる…!!
大団円とかでなく、単なるホモくせぇ結末になってしまってすみません…。
そんなつもりは更々ないのです。ほんとに。
アタイ、あんまりベッタベッタしてるSJ好きじゃないので。
ていうか有り得ないので。読む分には良くても書けない…。
まーなんだ、途中で松本がちょっと見せた切ない表情の理由は、
切ない系バージョン後書きを読んで頂けると。
なんとなくね、こっち(大団円)は、ちょっとオトナな松本。
切ない系は、ちょっとコドモな松本がテーマです(今作った←こら)。
| 1981年10月04日(日) |
どんなことばで***切ない系結末ver. |
薄暗い公園に全力疾走で駆け込むと、勝手に自分を待っているその傍迷惑な奴の姿は、すぐに目に付いた。
低いレンガの塀に浅く腰かけ、ただ空を見上げている。
数メートル手前で足を緩めると、相手もこちらに気づき、ふと左手首のアナログ時計に目をやった。
「2分30秒遅刻」
時計をわざわざ櫻井に見えるように顔の横に持ってきて言う。
「何様、だよ、おまえ」
両手を膝について肩で息をしながら、櫻井は松本のご丁寧な悪態に一応のパンチを入れる。
が、松本は知ったことかというように、塀から腰をあげると右手に握り締めていた物を櫻井の前に差し出した。
「はい、忘れ物」
顔をあげると、そこには月の光が反射されたシルバーの指輪。
確かにそれは、この数日間、櫻井の右手人差し指を寂しくさせていたものだった。
やっと手元に戻ってくると思うとほっとする気持ちもあるが、
このちっぽけなリングが、全てをおざなりにできない今の状況を作ったかと思うと、呪ってやりたくもなる。
いや、元はといえばそれを忘れた自分が悪いのだが。
櫻井は膝から手を放し、呼吸をできるだけ整えてから、それを受け取ろうと手を伸ばした。
「さんきゅ、悪かっ」
たな。と、櫻井は言い終えることができなかった。
目の前に差し出されたそれを、この手にする事ができなかったから。
渡される直前で、松本の手が指輪ごと空を仰いだから。だ。
しかし、そんな松本の行動に大した驚きがない自分に、ため息を吐きそうになる。
「結局さぁ、なんなの」
右手の上で指輪を転がしながら、松本は言った。
前の会話から全く繋がっていないその質問の意味も、今の櫻井は理解できてしまう。
数分前の電話の後、スタジオの廊下を走り始めたあの時から、この瞬間がくることはわかっていたから。
伸ばしていた手を重力にまかて下ろすと、ジャケットのポケットに突っ込んだ。
「どっちが」
松本のことなのか、それとも、事の発端となったあの日の電話の相手のことなのか。
「どっちでも」
松本も、櫻井の適応能力を当然のように受け止め、瞬時に切り返してくる。
ふたりの距離は、50センチ。体を向かい合わせたまま、しかし視線は合わせぬまま、沈黙が落ちた。
「単刀直入に聞こうか?つまり俺は翔くんにとってどの」
「ストップ」
またも沈黙を破った松本の問いを、櫻井は遮った。
わかっている。もう、わかっている。松本が何を言いたいのかも。自分にどう応えて欲しいのかも。
だが、その先にあるものは、まだ見えてない。
答えることによって、何かが崩れてしまうことだけはわかってるけれども。
口を噤み、ただじっと櫻井の応えを待つ松本。
視線を合わせると、櫻井はやっとの思いで口を開いた。
「お前が考えてること、わかってんよ。どう言って欲しいのかも、わかってる」
櫻井の意外な切り返しに、松本は一瞬眉を寄せたが、すぐに本題に戻してきた。
「じゃあ答えてよ」
まっすぐ自分を見つめる瞳。その瞳の持つ無駄な重みに、どれだけ苦しめられてきた事か。
でも、もうそれもお終いにしなければならない。
「ていうかさ、お前はその答えを俺に言わせてどうすんだよ」
「俺の希望通りの答えじゃないってこと?」
妙な威圧感を持つ声と共に、白い息が口から漏れる。
「まだその質問自体が当たってるかどうか、わかんないじゃん」
「わかってるって言ってんだろ」
半ばヤケクソ気味の声で、櫻井は答えた。
「はぁ?何それ。俺の考えてる事わかんの?あんたエスパー?」
相変わらず口の減らない松本は、やってられねぇよと言った風に、肩をすくめてみせる。
その仕草を見て、櫻井は自分の中で何かがぶち切れる音を聞いた。
「わかるよ」
突然静かに響いた櫻井の言葉に、松本は目を見開いた。
「お前のことなら、なんでもわかる」
櫻井自身、不思議な気持ちだった。
落ち着いているのか、どうでもよくなってしまったのか、自分でもわからない状態になっている。
「うざいんですけど、そういうの」
松本は一瞬だけ目を合わせたかと思うと、すぐに顔ごと逸らし、視線を空に泳がせた。
初めての反応。櫻井は、何かを掴んだ。
「俺の気持ちだろ」
ほんの少しだけ、松本との距離を詰める。
「やっぱ良いや。もう」
松本は視線を泳がせたまま、距離を計るように一歩後ろに下がった。
「良いやじゃねぇ、聞け」
それでも強引に歩を進める櫻井。こうなったらもう、最後の最後まで決着をつけるしかない。
「はい、指輪。返す。じゃあね」
松本はずっと握っていた指輪を、強引に櫻井のジャケットのポケットに押し込むと、踵を返した。
「待てって」
慌てて後を追う。松本は振り返らない。
「お前は俺の一番じゃねーよ。けど」
ついに口から出たその言葉。
一番じゃないけれど。
その先、櫻井が言いたいことは、松本もわかっている筈。ずっと前から、わかっていた筈だった。
それをわかってて問うてきた松本の本心が、わからない。
いや、わかる。いや、わからない。
「放せ」
いつの間にか松本の腕をしっかりと掴んでしまっていたことに、櫻井はやっと気がついた。
だが、放せない。
もう、自分でも何がどうなっているのか、わからない。
今この腕を放せば、明日、松本と自分は、何もなかったように接することが出来るだろう。
いや、もともと何もないのだから。
なのに、なのに、この心の奥にある隔靴掻痒の感は何なのか。
明日、松本がいつも通りの笑顔で話しかけてくる。
そんなビジョンを想像するだけで、櫻井の頭はおかしくなりそうだった。壊れてしまいそうだった。
「オンリーワンじゃ、意味ないから」
そう独り言ちた松本の頬に涙が流れていたことも、櫻井はわかっていた。
自分は間違ってないはずなのに。そう、出された問題用紙に、答えを書き込んで提出しただけなのに。
後悔としか言いようのない気持ちが、止まらない。
だがもし、松本の望むとおりの応えを自分が吐いたとして、はたしてそれで彼は満足しただろうか。
それはわからないけれども。
今の状況は、その仮定より悪い方向に進んでいる事だけはわかる。
「…っ」
一瞬櫻井が口を開きかけると、その空気を読み取ってか、松本が制止した。
「あやまんな」
目の前が真っ白になる。もう、戻れない。
明日、松本がいつも通りの笑顔で話しかけてくる。
その時、自分は…。
櫻井が半ば茫然自失に手を放すと、松本は一瞬だけコートの袖で目元をこすり、歩き出した。
後は追えない。追う資格などないと、わかっていた。
松本は、一度も振り返ることなく、公園から姿を消した。
残された櫻井は、ただ立ち尽くしたまま。
ポケットの中で、松本の体温の残るシルバーの指輪を、強く、強く握り締めることしかできなかった。
自ら断ったわけじゃない。ここ数年続いていた、松本と自分を繋ぐ細い糸を。
なのに、この罪の意識はなんなのだろう。
「冤罪だ」
ひとつ大きく白い息を吐くと、櫻井は、自分の頬を流れる水滴に気付かないフリをし、歩き出した。
end.
後書き。
解説して良いですか。ダメって言われてもする。
ほんとにどうにもこうにもマコッちゃんな結末で申し訳…。
なんつーの、ワタシの中のさっくんにとって、
松本はナンバーワンじゃなくてオンリーワンで。
松本にとってのさっくんはオンリーワンでもあるけど
それ以上にナンバーワンなのね。
だから、松本が「俺は翔くんがナンバーワンだから、
翔くんにとっての俺もナンバーワンじゃなきゃ嫌」
みたいな感じを書きたかったんでした。
でもさっくんて、ウソでも
「わかった。お前は俺のナンバーワンだよ」
とか言わなそうなんだよね。あくまでワタシの中でね。
あの人の愛情は、色んな人に100パーセントづつって感じだからさ。
そんで、松本もそれわかってんだけど、
でもやっぱりナンバーワンが良いと。そこはこだわるよと。
あの子「一番」てのが好きだし(AorNとか見て思った)。
なので、こんな結末になってしまったのでした。
切ない系ってか救いがないよ系?ほんとすいません。
どんなことばで
「おーわかった。んじゃまた連絡するわ」
別段とりとめもない話をした後、電話を切ると、部屋の中に静かな空間が帰って来た。
フリップを閉じた携帯をベッドの上に軽く放り投げ、手持ち無沙汰になる。
荷物の整理でもするか。と、櫻井はベッドに胡坐をかくように座りなおし、持ってきたバッグを引き寄せた。
と。隣のベッドに寝転び、読んでいた雑誌から目を離さないままの松本が、なんとなしに口を開いた。
「翔くんてさぁ」
返事もしないし顔も向けないが、聞いてますよ。というオーラだけは出しておく。
「まだ裕貴くんと続いてんだ?」
瞬間、櫻井の動きが止まった。
何を言い出すのか。というか、会話を聞いて勝手に相手を予想するな。というか、その質問にどう返せと。
言葉を失う櫻井。
ゆっくり首だけを、わけのわからない質問を投げかけた松本に向けた。
「あ、ごめん言い方おかしかった」
櫻井の視線に気づき、松本も雑誌から目を離すと、顔だけを向かい合わせる。
その表情は、自分の発言の妙に今気づきました。というものでは決してなくて。
絡み合った視線の先にある黒い瞳の重みに耐え切れず、櫻井は思わず目を逸らした。
「おかしすぎだろ」
荷物の整理を始めたはずなのに、出したものをまた戻すだけの作業になっている。
その動きを見て、松本の目もまた雑誌に戻るが、果たして内容は頭に入っているかと言えばそれは皆無。
「嫉妬してるんじゃないから安心して」
少しわざとらしいフォロー。声も無駄に笑わせているのはわかるが、表情は確認できない。
それがリアルで嫌なんだよ。
櫻井の眉間に皺がよる。舌打ちしそうになったが、こらえた。
「って、お前はオレのなんなんだよ」
つられたようにわざとらしく笑いながらも、話し相手に顔は向けない。向けられない櫻井。
松本からも、答える気配は感じられない。
バッグの中は、整理したはずなのに開ける前よりも乱れてしまったが、もう一度出すのも白々しい。
結局そのままにしてジッパーを閉じると、その音が妙に大きく響いた気がした。
隣の人間は、雑誌を読んでいるはずなのに、ページをめくる音すらしない。
訪れる静寂。
「なんなの?」
壊したのは、松本だった。
声の主に顔を向けると、いつの間にか松本もまた櫻井を見ていた。
視線がかち合うと、開いているだけだった雑誌を閉じ、立てていた腕を顎の下で組んで、うつ伏せになる。
が、櫻井から見える左目だけは、こちらに向けたまま。
「オレが聞いてんだよ」
「オレもわかんないもん」
うって変わって、すぐさま答えが返ってくる状況。
反則だろ。
問いに対する問いは、松本の十八番だろうけれども。わかっていてやってるのだろうけれども。
それがまた、櫻井に苛立ちを募らせる。
自分の問いに自分で答える義務などない筈なのに、そうはいかない雰囲気にさせられているのは何故か。
まっすぐ自分を見つめる瞳。少しだけ、視線を横にずらして言う。
「バカ、メンバーだろ」
やっとの思いで出た言葉は、当たり前すぎて、逆に、棒読みのようになってしまった気がする。
「知ってる」
予想してましたと言わんばかりの抑揚のない声で答えた松本は、瞼を閉じ、顔を枕と腕の中に沈めた。
表情が見えなくなって、なぜか櫻井はほっとする。
じゃあ聞くなよと言いたくなるのを抑えて、無意味に頭を掻いた。そういうことじゃないのはわかってて言った。
ここで自分がそう持っていっても、相手が同じ方向に取り合ってくれるはずはなくて。
だからといって、そこに松本が求めているのだろううまい表現を、さらりと当てはめられる自信もない。
大体にして、今更そんな質問をしてくる松本の方がどうかしている。
なんなんだ。
ため息をひとつ、松本に気づかれないくらい小さく吐く。
空白の時間に耐え切れなくなった櫻井は、もう一度バッグを開けると、ポータブルCDプレイヤーを出した。
適当なCDをセットし、イヤホンを当てようとした時。
「裕貴くんは、なんなわけ?」
タイミングを計ったように、新たな問いかけ。顔は、埋めたまま。
先ほどから引っ張り出された名前は、櫻井にとって、松本を含む嵐のメンバーとは別に大切な友人のもので。
昔は仕事仲間として。今はプライベートでの付き合いがある。
勿論松本も知っている。
なぜ今更、それを引き合いに出してくるのか。本当にどうかしている。更に募る苛立ち。
付き合いきれねぇよ。
問われても、櫻井の顔は、もう相手には向かなかった。松本の表情は、読まない。答える必要は、ない。
「おまえ、うざい」
反応が返ってくる前に、櫻井は乱暴にイヤホンを耳にあて、音量最大で演奏開始ボタンを押した。
櫻井がその忘れ物に気づいたのは、ホテルを出て大分経ってからだった。
マネージャーに聞いてみたが、ホテル側からも、それらしきものは見つからなかったと返ってきたらしい。
直感。松本が持ってる。
結局ふたりはあの後一言も会話を交わさず別れ、それから、会っていない。
互いのスケジュールの所為もあるが、電話もメールもせずに数日経っているというのは、かなり稀有だろう。
今日は週のど真ん中、水曜。あと3日もすれば、生番組でどうせ会う。
連絡せずとも持ってきてくれるのが人ってもんだろうと、櫻井は勝手に自分を納得させていた。
だが、渡される時のことを考えると、また一悶着あるかもわからない。
「…めんどくせぇ」
いつもはある筈の指輪の位置…右手の人差し指を、無意識に親指でいじりながら、櫻井は小さく独り言ちた。
「翔くん、寝てんの?」
ひとり車の中でまどろんでいたところに急に声をかけられ、櫻井は今に引き戻された。
「おはよ、さとっさん」
乗り込んできたのは、大野。今日はふたりで雑誌の取材。マネージャーの運転する車で、撮影場所に向かう。
おはようと小さく返しながら、大野は相変わらずのぼやけた瞳で思い出したように言った。
「松潤から伝言。どーすんの、アレ。って」
「アレ?」
思わぬ人物から思わぬ話題を振られ、櫻井は一瞬面食らったが、すぐに全てが読み取れた。
少し考え込んでいると、伝言の付け足し。
「言えばわかるから。って言われたけど」
大野に、詮索してくる様子はなかった。興味がないのか、聞いてはいけないと思っているのか。
どちらにせよ、当事者としては助かる伝言役だった。
それにしても、わざわざこんな伝言役をよこすとは、一体何の意図があってのことなのか。
何も言わず土曜に持ってくれば良いだけの話だろう。もしくはメールで一言よこすなり。
櫻井の中で、苛立ちというよりは気に食わないという気持ちがふつふつと湧き上がってきた。
受けて立とうじゃないの。
「じゃさ、悪いんだけど俺のも伝言してくんね?愛してるから捨てないでー。って」
体はシートに寄りかけたまま、捨てないでの部分だけ少しオーバーに手を伸ばして言う。
「はぁ?」
「言えばわかるから」
怪訝な顔の大野が面白くて、櫻井はわざと大野に顔を近づけ、松本の口ぶりを真似てみせた。
それが気に食わなかったのか、眉間に更なる皺を寄せ、大野は口をふくらませる。
「つーか自分で言えっ!」
「あははは!」
土曜まであと3日。伝言係が訳もわからず働いてくれるならば、それより前に何か松本からアクションがあるかもしれない。
笑いながらも、右手の人差し指の風通りの良さは、櫻井の心に反比例していた。
それはやはり金曜の夜に起こった。
櫻井が単独での雑誌の取材を終えた直後、タイミングを計ったようにかかってきた電話。
液晶に表示された名前は、勿論、松本潤。
スタジオの廊下を歩きながら、櫻井は適当な声でその電話に応えた。
電話の相手は、予想通り、名も名乗らず、挨拶もなし。不機嫌そのものの第一声はこうだった。
「なんなの、あの伝言」
いつになく低いトーン。感情は、読めない。
「伝わった?愛」
肩と首で携帯を挟み、櫻井は、誰が見てるわけでもないのに両手でハートマークを作って答えた。
が、電話の先からは当然、冷たい声。
「ふざけんな」
可愛らしい答えを期待していたわけでは決してないが、こうもあっさりあしらわれるとは。
自分のキャラ作りも相当虚しくなってくる。
「何、その態度。言ってほしかったんじゃないの?潤ちゃんてば」
わざとふざけた声にしてみせた。
少し強気に出れるのは、顔を、あの無駄にプレッシャーをかける瞳を見ずに話せるからだろうか。
「むかつく。捨てちゃおっかな、忘れ物」
当の松本は、むかついてるとは思えないほどの抑揚のない声で、すぱっと衝撃的なことを言ってみせた。
捨てられる筈はないとわかっていても、少し接し方を改めなければいけないらしい。
櫻井も、無駄な労力を消費しないように、本題に会話を促すことにした。
「はいはい。で、今どこにいんの?」
こうなったら一刻も早く忘れ物を取り返し、この刺々しい空気を、とまらない苛立ちを、和らげたい。
外にいるなら、帰りにでもマネージャーの車で寄ってもらえば、すぐだ。
面倒な事になる前に帰る口実もできる。
が、櫻井はその目論見を、瞬時にして消さざるを得なかった。
「…の公園」
「は?」
前半が聞き取れなかったのは、電波の調子でなく、わざと松本が声を濁して言ったからだとわかった。
聞き返すと、今度はその信じられない答えをはっきりと聞く事ができてしまったから。
「今翔くんがいるスタジオのすぐ近くの公園だよ」
「はぁ?!何やってんのお前!」
思わず声をあげると、コンクリート打ちっぱなしの廊下に反響し、櫻井は慌てて辺りを見回した。
誰もいないのを確認すると、すぐに思考に神経を戻す。
が、たった2,3秒前の、少し自棄的な声の松本の言葉が、櫻井には理解できなかった。
というよりは、理解したくなかったのか。
だが、混乱する櫻井をうっちゃって、松本は勝手に独りで話を進めてしまう。
「2分で来ないと、マジで捨てちゃうから」
勢い的に言い捨てられ、通話が切れた電子音が聞こえた。
「ちょっ…待てお前こら!」
一方的に切られた電話を強く握り締めて、聞こえるはずのない相手を必死で制止する。
無情にもその願いに応えるのは無機質な電子音だけなのはわかっていても、そうするしかなかった。
いつの間にか足は止まっていたらしい。先程から変わらぬ廊下の景色。
公園までは、どう頑張っても5分はかかる距離だ。
「っざけやがって…」
今や光を全く放たない携帯の液晶をきつく睨みつけ、乱暴にフリップを閉じると、櫻井は走り出した。
途中、マネージャーとすれ違うと、振り返りざまに送りはいらないとだけ伝え、スピードをあげる。
息が切れる。頭に血が上る。鼓動が、脈拍が、速くなっていくのがわかる。
そうさせてるのは、この走りなのか、それとも、気持ちなのか。
これだけ走って、辿り着いて、そこで、自分は松本に何を言うのだろう。何が言えるのだろう。
あの問いへの答えは、まだ出ていないのに。
いや、出ているのかもしれない。ただそれを、言葉にしたくないだけで。
賽は投げられた。一方的に。
ここから先のお話は、2パターンに分かれております。お好きな方を選んでどうぞ。
○ちょいと破滅的なSJがお好きな方はあっち
○仲良しラブラブなSJがお好きな方はこっち
アラシのみ。徐々に増やしていければ。
***SJ
○どんなことばで
ちょっと長めのうだうだらだらストーリー。
結末が二つに分かれております。
一回で二度オイシイ☆(?)でもJSくさい。
○ブラックコーヒー
SJにしては甘ったるい感じなオハナシ。
短いです。
***NA
○5manths+24days
アイバちゃんお誕生日記念小咄。(小咄?)
ニノミ視点で、ほぼ会話。
小説とは言い難いけどまぁ…一応。
| 1981年10月01日(木) |
INFOMATION |
ハジメマシテ!コンニチワンツー!ダメ人間saikoのダメダメ日記へようこそ。
Tihs page last up date 20040908
【取り扱い】
・テニプリ・・・乾海 ・アラシ・・・SJ・NA ・音楽…ヒプホプ
【地図】
・ハジメマシテ・・・ここ。
・オエビ・・・気が向いたら描いてる。
・ノベル・・・今のとこ長編小説1本・短編1本。両方SJだす。
・リンク・・・お好きにどうぞー。
【書いてる人】
名前→saiko(「さいこ」と読むべし)
年齢→20代前半
and more→前略プロフィール
【同人活動】
saiko個人サークル【psy;logic】
アラシオールメンバー・SJ・NA中心で活動中。
東京の大きめのイベントにチラホラ出てます。
WEB通販の予定はあんまりないので、イベントでペーパーをゲトって下さい。
・イベント参加予定
10月 City アラシスペース
12月 冬コミ 受かれ
 ○ハジメマシテ
○オエビ
○ノベル
○ダイアリー
○ハジメマシテ
○オエビ
○ノベル
○ダイアリー ○ハジメマシテ
○オエビ
○ノベル
○ダイアリー
○ハジメマシテ
○オエビ
○ノベル
○ダイアリー