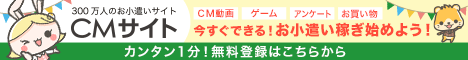| 1981年10月04日(日) |
どんなことばで***切ない系結末ver. |
薄暗い公園に全力疾走で駆け込むと、勝手に自分を待っているその傍迷惑な奴の姿は、すぐに目に付いた。
低いレンガの塀に浅く腰かけ、ただ空を見上げている。
数メートル手前で足を緩めると、相手もこちらに気づき、ふと左手首のアナログ時計に目をやった。
「2分30秒遅刻」
時計をわざわざ櫻井に見えるように顔の横に持ってきて言う。
「何様、だよ、おまえ」
両手を膝について肩で息をしながら、櫻井は松本のご丁寧な悪態に一応のパンチを入れる。
が、松本は知ったことかというように、塀から腰をあげると右手に握り締めていた物を櫻井の前に差し出した。
「はい、忘れ物」
顔をあげると、そこには月の光が反射されたシルバーの指輪。
確かにそれは、この数日間、櫻井の右手人差し指を寂しくさせていたものだった。
やっと手元に戻ってくると思うとほっとする気持ちもあるが、
このちっぽけなリングが、全てをおざなりにできない今の状況を作ったかと思うと、呪ってやりたくもなる。
いや、元はといえばそれを忘れた自分が悪いのだが。
櫻井は膝から手を放し、呼吸をできるだけ整えてから、それを受け取ろうと手を伸ばした。
「さんきゅ、悪かっ」
たな。と、櫻井は言い終えることができなかった。
目の前に差し出されたそれを、この手にする事ができなかったから。
渡される直前で、松本の手が指輪ごと空を仰いだから。だ。
しかし、そんな松本の行動に大した驚きがない自分に、ため息を吐きそうになる。
「結局さぁ、なんなの」
右手の上で指輪を転がしながら、松本は言った。
前の会話から全く繋がっていないその質問の意味も、今の櫻井は理解できてしまう。
数分前の電話の後、スタジオの廊下を走り始めたあの時から、この瞬間がくることはわかっていたから。
伸ばしていた手を重力にまかて下ろすと、ジャケットのポケットに突っ込んだ。
「どっちが」
松本のことなのか、それとも、事の発端となったあの日の電話の相手のことなのか。
「どっちでも」
松本も、櫻井の適応能力を当然のように受け止め、瞬時に切り返してくる。
ふたりの距離は、50センチ。体を向かい合わせたまま、しかし視線は合わせぬまま、沈黙が落ちた。
「単刀直入に聞こうか?つまり俺は翔くんにとってどの」
「ストップ」
またも沈黙を破った松本の問いを、櫻井は遮った。
わかっている。もう、わかっている。松本が何を言いたいのかも。自分にどう応えて欲しいのかも。
だが、その先にあるものは、まだ見えてない。
答えることによって、何かが崩れてしまうことだけはわかってるけれども。
口を噤み、ただじっと櫻井の応えを待つ松本。
視線を合わせると、櫻井はやっとの思いで口を開いた。
「お前が考えてること、わかってんよ。どう言って欲しいのかも、わかってる」
櫻井の意外な切り返しに、松本は一瞬眉を寄せたが、すぐに本題に戻してきた。
「じゃあ答えてよ」
まっすぐ自分を見つめる瞳。その瞳の持つ無駄な重みに、どれだけ苦しめられてきた事か。
でも、もうそれもお終いにしなければならない。
「ていうかさ、お前はその答えを俺に言わせてどうすんだよ」
「俺の希望通りの答えじゃないってこと?」
妙な威圧感を持つ声と共に、白い息が口から漏れる。
「まだその質問自体が当たってるかどうか、わかんないじゃん」
「わかってるって言ってんだろ」
半ばヤケクソ気味の声で、櫻井は答えた。
「はぁ?何それ。俺の考えてる事わかんの?あんたエスパー?」
相変わらず口の減らない松本は、やってられねぇよと言った風に、肩をすくめてみせる。
その仕草を見て、櫻井は自分の中で何かがぶち切れる音を聞いた。
「わかるよ」
突然静かに響いた櫻井の言葉に、松本は目を見開いた。
「お前のことなら、なんでもわかる」
櫻井自身、不思議な気持ちだった。
落ち着いているのか、どうでもよくなってしまったのか、自分でもわからない状態になっている。
「うざいんですけど、そういうの」
松本は一瞬だけ目を合わせたかと思うと、すぐに顔ごと逸らし、視線を空に泳がせた。
初めての反応。櫻井は、何かを掴んだ。
「俺の気持ちだろ」
ほんの少しだけ、松本との距離を詰める。
「やっぱ良いや。もう」
松本は視線を泳がせたまま、距離を計るように一歩後ろに下がった。
「良いやじゃねぇ、聞け」
それでも強引に歩を進める櫻井。こうなったらもう、最後の最後まで決着をつけるしかない。
「はい、指輪。返す。じゃあね」
松本はずっと握っていた指輪を、強引に櫻井のジャケットのポケットに押し込むと、踵を返した。
「待てって」
慌てて後を追う。松本は振り返らない。
「お前は俺の一番じゃねーよ。けど」
ついに口から出たその言葉。
一番じゃないけれど。
その先、櫻井が言いたいことは、松本もわかっている筈。ずっと前から、わかっていた筈だった。
それをわかってて問うてきた松本の本心が、わからない。
いや、わかる。いや、わからない。
「放せ」
いつの間にか松本の腕をしっかりと掴んでしまっていたことに、櫻井はやっと気がついた。
だが、放せない。
もう、自分でも何がどうなっているのか、わからない。
今この腕を放せば、明日、松本と自分は、何もなかったように接することが出来るだろう。
いや、もともと何もないのだから。
なのに、なのに、この心の奥にある隔靴掻痒の感は何なのか。
明日、松本がいつも通りの笑顔で話しかけてくる。
そんなビジョンを想像するだけで、櫻井の頭はおかしくなりそうだった。壊れてしまいそうだった。
「オンリーワンじゃ、意味ないから」
そう独り言ちた松本の頬に涙が流れていたことも、櫻井はわかっていた。
自分は間違ってないはずなのに。そう、出された問題用紙に、答えを書き込んで提出しただけなのに。
後悔としか言いようのない気持ちが、止まらない。
だがもし、松本の望むとおりの応えを自分が吐いたとして、はたしてそれで彼は満足しただろうか。
それはわからないけれども。
今の状況は、その仮定より悪い方向に進んでいる事だけはわかる。
「…っ」
一瞬櫻井が口を開きかけると、その空気を読み取ってか、松本が制止した。
「あやまんな」
目の前が真っ白になる。もう、戻れない。
明日、松本がいつも通りの笑顔で話しかけてくる。
その時、自分は…。
櫻井が半ば茫然自失に手を放すと、松本は一瞬だけコートの袖で目元をこすり、歩き出した。
後は追えない。追う資格などないと、わかっていた。
松本は、一度も振り返ることなく、公園から姿を消した。
残された櫻井は、ただ立ち尽くしたまま。
ポケットの中で、松本の体温の残るシルバーの指輪を、強く、強く握り締めることしかできなかった。
自ら断ったわけじゃない。ここ数年続いていた、松本と自分を繋ぐ細い糸を。
なのに、この罪の意識はなんなのだろう。
「冤罪だ」
ひとつ大きく白い息を吐くと、櫻井は、自分の頬を流れる水滴に気付かないフリをし、歩き出した。
end.
後書き。
解説して良いですか。ダメって言われてもする。
ほんとにどうにもこうにもマコッちゃんな結末で申し訳…。
なんつーの、ワタシの中のさっくんにとって、
松本はナンバーワンじゃなくてオンリーワンで。
松本にとってのさっくんはオンリーワンでもあるけど
それ以上にナンバーワンなのね。
だから、松本が「俺は翔くんがナンバーワンだから、
翔くんにとっての俺もナンバーワンじゃなきゃ嫌」
みたいな感じを書きたかったんでした。
でもさっくんて、ウソでも
「わかった。お前は俺のナンバーワンだよ」
とか言わなそうなんだよね。あくまでワタシの中でね。
あの人の愛情は、色んな人に100パーセントづつって感じだからさ。
そんで、松本もそれわかってんだけど、
でもやっぱりナンバーワンが良いと。そこはこだわるよと。
あの子「一番」てのが好きだし(AorNとか見て思った)。
なので、こんな結末になってしまったのでした。
切ない系ってか救いがないよ系?ほんとすいません。
 ○ハジメマシテ
○オエビ
○ノベル
○ダイアリー
○ハジメマシテ
○オエビ
○ノベル
○ダイアリー ○ハジメマシテ
○オエビ
○ノベル
○ダイアリー
○ハジメマシテ
○オエビ
○ノベル
○ダイアリー